INFORMATION TITLE【野球肘を根本的に治すために必要な知識と治療方法】
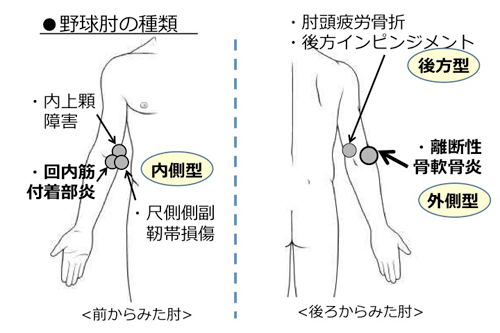
「野球肘の痛みを早く治したい」
野球肘になると投球をするとき肘が痛いだけではなく、また痛みが起こるんじゃないかと次第に投げるのが怖くなります。
それでも無理をして投球を続けると痛みをかばうようなピッチング動作になり、本来の正しい動作ができなくなってしまいます。
身についてしまった悪い投げ方を修正するのには時間がかかります。
また、肘をかばうあまりに、今度は肩を痛めてしまう場合もあります。
そうなると肘だけではなく、肩まで回復させなければいけなくなります。
小学生、中学生の野球選手に多い症状です。
大切な大会が迫ってくると野球をしたい、レギュラーに入りたいという気持ちが出てきて焦ってしまいます。
その気持ちはよくわかります。
ですから肘に痛みを感じたら、できるだけ早めに適切な治療方法を行っていくことを考えてください。
「でも、熱心に野球をしていれば、少しくらい肘が痛くなるものなんじゃないですか? チームメイトに置いていかれたくないから、練習や試合は休みたくないんです。だから、痛みとうまく付き合いながら、練習に参加するしかないんです」
と言いたい気持ちはよくわかります。
しかし、指導者や先輩のチームメイトによる
「一生懸命、練習をしていたら多少の肘の痛みは仕方がない」
「痛みと付き合いながら練習をするのが当たり前だ」
「練習を休んだから肘が良くなるものではない」
というアドバイスは本当にあなたのためになるでしょうか?
野球肘は適切な対処をすれば、痛みが無くなっていく可能性は十分あります。
もちろん症状の度合いやその人の治癒力、練習を休めるかどうかによって、回復までのスピードはそれぞれ違いますが、良くすることに専念できれば1か月前後で野球に復帰できる方が多いです。
また、練習をしても再発しないようにケアのアドバイスもしていきます。
やみくもに治療方法を試すのはやめて、野球肘の原因を正しく知り、お教えしたセルフケアをやってどんどん症状が良くなっていっています。最終的には思いきりボールを投げても痛くなくなります。
これから野球肘になった原因と、早期回復のために必要なことをあなたにお伝えします。
<野球肘とはどのような症状なのか?>
野球肘の症状は、
●ボールを投げると肘が痛い
●全力でボールを投げることが怖い
●レントゲンを撮っても異常がなかった
●筋トレをするように勧められた
などが挙げられます。
ひどくなると、バットを振る時も痛みが出たり、普段の生活でも雑巾やドアノブを回すと痛みを感じるようになります。
野球肘の種類は、野球肘は、「内側型」・「外側型」・「後方型」の3つに分類されます。
肘の内側が痛む「内側型」は小学生、中学生、高校生に多く
肘の外側が痛む「外側型」は小学生に多く
肘の裏側が痛む「後方型」は高校生、大学生に多いです。
【 内側型 】
肘の内側が痛みます。
疾患名でいうと「上腕骨内側上顆炎」や「内側側副靭帯損傷」などが内側型に当てはまります。
一般的には、前腕にある屈筋(手首を掌側に曲げる筋肉)が引っ張る力、ボールを投げる際に肘にかかる外へのひねる力が、くり返しかかることで、肘が痛むと言われています。
成長期の子供の場合、骨端線という成長軟骨があり、靭帯や筋肉が骨端線の部分を繰り返し引っ張る事で骨端線の部分がずれを起こし痛みが起こるとされています。
【 外側型 】
これは肘の外側が痛くなるタイプです。
疾患名でいうと「上腕骨小頭離断性骨軟骨炎」が中心になります。
上腕骨小頭断性骨軟骨炎は、投球時に起こる過度の外へのひねる力によって肘関節の骨同士がぶつかり合い、上腕骨の下の方にある軟骨部位が徐々に剥がれてきて起こるとされています。
外側型は成長期の子供(小学生)に多いようです。
【 後方型 】
後方型は肘関節の後方が痛くなります。
これは、肘関節を伸ばした時に、肘関節を構成する骨同士が衝突し合いって痛む場合があるとされています。
また、腕の力こぶの逆側の筋肉(上腕三頭筋)が過剰に収縮することで痛みを起こすこともあると言われています。
<野球肘が治らない理由①野球肘の原因に対する認識の間違い>
病院や整形外科では、正しい野球肘の原因を教えてもらうこともあれば、
「痛くなったら投げないでね。」と、痛み止めとシップを渡されて「様子を見てください」と言われる方もいると思います。
ですから、まずは、野球肘の正しい原因を理解していきましょう。
野球肘は、ボールを投げる投球動作において肘に痛みがあれば、野球肘が疑われ、レントゲンやMRIやエコーなどの画像により骨折の状態から診断します。
特に、まだ体が柔らかい10代の頃に激しく投球動作をくり返すことで、肘の骨の一部が過度に伸ばされたり、関節内の衝突により痛みを起こすわけですが、そもそも、そのようにして痛みを起こしたのは、そうさせてしまう理由が必ずあるわけです。
ですので、骨に着目することより、骨に痛みを起こした原因の方が重要で、そこを解消しないと、仮に痛みが消えて野球を再開しても、また痛みが戻ってきてしまうことがあります。
<痛みのメカニズム>
「肘の骨が痛い」と思ってしまいがちですが、実は骨には痛みを感じる神経がありません。
痛みを起こしているのは、骨の周辺の神経や骨にくっ付く硬くなった筋肉によって起きていると考えています。
肘は、肩や手首や指先の筋肉がたくさんくっ付く場所です。
投球動作はそれらたくさんの筋肉が、肘を含めて腕全体を捻じることで可能になります。
肘関節はそう簡単には痛む場所ではありませんが、スピードを伴う捻じれの動きに関しては、関節が複雑に動くことになるので周辺の筋肉の柔軟性が必要になります。
しかし、硬くなった筋肉が投球動作に関係していると肘を強く引っ張って大きな負担になります。その繰り返しがやがて肘の炎症やひどくなると骨のはく離を起こすと考えられます。
ですので、骨の状態にもよりますが、肘に関わる筋肉の柔軟性を取り戻すことで、肘の骨に異常があっても、痛みを感じず思いっきりボールを投げることが可能な場合もあります。
<肘だけの原因ではなく、手の指が関係している>
肘には、指先や手首からつながっている筋肉がたくさんくっついています。
ボールを投げる時には、この筋肉が柔らかく伸び縮みするのです。
例えば、シャドウピッチングのときは痛くないのにボールを持って投げたときだけ痛いという場合は、ボールを持ったときにだけ使われる筋肉、いわゆる手の指の筋肉が大いに関係してきます。
野球肘の多くの患者さんは、リラックスしている時も指先がグーのように曲がっています。
普段の生活の中でも指先に負担をかけている、クセも含めて指先の柔軟性を取り戻していきます。
そうすることで、肘の痛みが改善することはもちろん、肘への負担が減るので、以前より球速を増す方も多くいらっしゃいます。
<全身の筋肉の柔軟性を出すことが大切>
ボールを投げる時は、どの野球選手も必ず足を上げて踏み出し、そこから得られるエネルギーを体幹から肩、肘、そして指先のボールに伝えるという全身使う動きから投球動作は生まれます。
その全身の動きの一つでも上手く働かない場所があると、そのしわ寄せの多くは肩や肘にくるのです。
野球肘になる人の特徴には、股関節と肩甲骨の硬さが挙げられます。
股関節や肩甲骨などの大きな筋肉が硬くなってしまうこと、その先にある肘に大きな負担をかけることになります。
ですので、野球肘は投球の一連の動きを診ながら、肘に負担をかけている個所をしっかり取り除いていくことも大切なポイントです。
また、野球肘を治すためにフォーム修正に取り組まれている方が多いのですが、全身の柔軟性が取り戻せていない状態で、やみくもに投球フォームを修正することはかえって痛みを増すことになりかねないので
まずは、その人の本来の筋肉の柔らかさに戻すことを優先させましょう。
そして、体全体を整えたことで、その人本来の投球動作を取り戻すことができ
フォーム修正することなく、以前の様にボールを思いっきり投げている人も少なくありません。
<筋トレがかえって治りを妨げる >
野球肘の治療方法には、筋トレを紹介してくれる病院や治療院もあります。
手首や肘・肩回りなどトレーニングなのです。
なかさこ整骨院では、多くの野球肘の患者さんを診てきて、筋トレがかえって治りを遅くしていることを経験として理解しています。
確かに、筋トレは有効なコンディショニングづくりの方法ですがタイミングを間違えるとかえって痛みを起こし、パフォーマンスを落とす諸刃の剣なのです。
野球を経験した方なら一度はやったことがあるかも知れませんが、前腕を鍛えるリストカールといったダンベルを持って手首の曲げ伸ばしを繰返すものや、ひたすらグーパー運動するというトレーニングなどあります。
しかし、やった後は、疲労で前腕がカチカチになって動かすことも大変になりませんか?
これらの筋トレは、肘を動かす筋肉を縮める連続運動で、肘の引っ張りを強くして負担をかけてしまうので痛みを増すことになり、かえって治りを遅くしてしまいますので、痛みがあるうちは筋トレはお勧めできません。
<野球肘が治らない理由②野球肘に対する治療の間違い >
もし、野球肘を発症してから1ヶ月以上経過していても少し楽になったとか、痛みは変わっていなくてむしろひどくなっているのであれば、治療方法が間違っている可能性があります。
なかさこ整骨院では来院された患者さんから詳細に今まで行なった治療方法を聞きます。
それらをまとめると、
(1)アイシング
(2)湿布、スプレー式鎮痛消炎剤
(3)電気治療
(4)ストレッチ
(5)マッサージ
(6)超音波治療
(7)痛み止めの注射
(8)筋力トレ
(9)手術(野球肘で手術が必要と医師から言われた場合でも、回復する可能性はあります)
などが挙げられます。
これらの治療方法を否定している訳ではありません。
しかし、実際に上記の治療をしていても改善しない方がなかさこ整骨院には多く来院されますし、もし今の治療方法で結果が出ていないのであれば、方法を変えてみる必要があると考えています。
<現在の治療方法で治らない理由>
痛み止め、湿布、アイシング(患部を冷やす)などは多少楽になる方もいらっしゃるかもしれませんが、痛み止めをやめた後は痛みが戻ったり、さらに痛みが悪化してしまうこともあります。
これらの方法は、一時的に痛みを感じにくくすることはできても筋肉の柔軟性は変わっていないため、根本的な痛みの解決にはなっていないのです。
筋肉を柔らかくするためにマッサージ、指圧、干渉波・ドップラー波電療法(病院や接骨院でおこなう電気治療)、ストレッチをおこなって改善されていれば問題ありませんが、痛みを我慢しならが行うようなマッサージや電気治療、ストレッチは一時的に効いている気がしても、強い刺激で筋肉の組織が壊れてしまうこともあります。
すると体はその壊れた組織を回復する際に、再び壊されることがように。とどんどん強く硬くしてしまいます。ですから、痛みを我慢してマッサージやストレッチ繰り返してきた患者さんほど筋肉の緊張がより強くなっており、慢性化して改善しづらくなっていることが分かっています。
特に痛みのある状態の筋肉に対しての強いマッサージやストレッチはオススメできません。
筋肉を柔らかくしようと思ったら、筋肉の組織などを壊さないように緊張が起きないように働きかけをして、柔軟にしていく必要があるのです。
そのため、原因は理解していても、その原因に対しての治療方法が間違っていると痛みが改善しないのです。
また、一度、良くなったと思っても練習を再開すると痛みが戻ってしまう患者さんもいます。これは、なぜでしょうか?その理由を次にお話ししていきます。
<野球肘が治らない理由③「痛くない=治った」の間違い>
これまでになかさこ整骨院に来院された野球肘の患者さんの中には「しばらく休んで痛みがないから腕が振れそうだ!と思ってボールを投げてみると痛みが戻ってきてしまいました。」と言われる方も多くいらっしゃいました。
これには理由があります。
野球肘が治ったわけではなく、痛みを感じなくなっただけで野球肘を引き起こしてしまう要因が根本的に解消されていないことが考えられます。
野球肘は、「急激な負荷がかかったから疲労骨折が起きた」わけではなく、動き方やクセ、練習環境などによって違いはでてきますが、これまでの習慣の中で野球肘を引き起こしてしまう要因があったため起きる症状です。
その習慣が残っている限り、ふたたび痛みが出てくる可能性が高まります。
ですから、痛くない=治ったというのは間違いです。
では、一体どうしたら根本的な解決ができるのでしょうか?
なかさこ整骨院が多くの野球肘を根本的に解消していくための考え方をご紹介します。
<野球肘を改善するための3つの治療方法>
これまでお話してきたことを踏まえて、野球肘は正しい原因を理解して、その原因に対して適切な治療をして、再発が起きないような体作りができればきちんと改善します。
具体的になかさこ整骨院では、野球肘に対して以下のような施術をおこなっていきます。
<①腕、手首、指などの筋肉の緊張を柔軟にする>
ボールを投げる時に、スピードを上げようとして指先のスナップに頼りすぎてしまうと、肘に負担がかかります。
もしくは、肩の痛みをかばって投げているうちに、末端の指に負担をかけ、肘を痛めてしまうこともあります。
野球肘は、「急激な負荷がかかったから痛みが起きた」わけではなく、もともと腕や手首や指の筋肉に疲労がたまっていて、筋肉の柔軟性が低下していたところに負荷がかかったために起きたケガなのです。
もし、筋肉に柔軟性があれば、筋肉自体が衝撃を吸収してくれるため肘への負担が減ります。
野球肘になった人は、共通して、腕や手首や指の筋肉がガチガチに固くなっているのです。
それら、緊張している(硬くなっている)筋肉は強い刺激を与えるとさらに緊張が強くなってしまうので、痛くない(緊張が起きない)範囲で働きかけをして、柔軟にしていきます。
<②背中、肩甲骨、股関節など体全体のつながりの筋肉も柔らかくする>
野球肘は、腕、手首、指などの筋肉の硬さだけでなく、投球動作に関係する筋肉を柔らかくしていく必要があります。
特に、背中や肩甲骨と股関節を柔軟にすることで、複雑な投球動作では、肘だけに負担をかけずに背中や肩甲骨など体全体を使って動かすことができるので、より大きく、より力強く、よりスピードを増すことができるようになります。
<③復帰の方法やご自身でできるセルフケアを伝えます>
野球肘の痛みが軽減されてきたら、ご自身でできるセルフケアもお伝えしていきます。
ご自身でもセルフケアを行いながら、施術を受けることでより回復しやすくなります。
小・中学生の野球肘なる子に聞き取りをすると、猫背でゲームを長時間しているケースが多いようです。
姿勢や指先を酷使することで、肘に負担をかけることは普段の生活の中にもあります。
なかさこ整骨院では、生活習慣も含めて具体的にアドバイスしていき、復帰の段階では、必要に応じて、練習環境、練習方法なども伝えていきます。
体の柔軟性が取り戻されると筋肉が硬くなっていたことで起きていた動きの制限やクセなども修正されて、その人に合った本来の体の動きに戻っていくため、練習を休んでいたにもかかわらず、パフォーマンスがアップする選手も少なくありません。
<野球肘の改善を遅くしている要因>
筋肉の緊張以外にも野球肘の治りを妨げているものがあります。
監督や先輩の野球肘やスポーツ障害への理解の無さが、改善を妨げていることもあります。
・練習を休みたいから、少し痛いだけなのに大げさに言っているんだろう
・この子はやる気がない。もっとやる気がある子を試合に出そう
・筋力が弱いから痛くなるんだ。筋トレをして鍛えなければならない
また痛みを抱えている本人も、
・先輩もいろんなところが痛くても練習をしているのに、自分だけ休みたいなんて言えない
・どうせ休んだって、練習を再開したら、元に戻ってしまうんだから、上手に付き合っていく方がいい
と考えていることが野球肘の痛みを改善しにくくしています。
しかし、監督や先輩の目を気にしながら痛みをガマンしながら練習をしつづけて、練習ができないほど肘が悪化をしてしまったとき、周りの人は「一生懸命、練習をしてきたな。今まで頑張ったな」とは言ってくれません。
「なぜ、もっと痛くなる前にケアをしなかったんだ」と言われて悔しい思いをすることになるでしょう。
そして、監督や先輩はあなたの野球肘を改善してくれません。
あなたの体は自分で良くしていくしかないのです。
<保護者の方へ>
お父さん、お母さんにとってもお子さんの肘の痛みはとても心配だと思います。
外から見て、傷があるわけではないので人から痛みを理解してもらえないことも、ストレスになっているかもしれません。
チームに混ざって同じように野球ができないお子さんを見ているのは辛いと思います。
だからこそ、野球肘は早期に改善させなくてはいけません。
適切に対処するのが、早ければ早い方が野球肘は回復していきます。
「投げると痛いかな」「ガマンして投げなきゃ」と痛みをかかえながら生活をするのは精神的にも良くありません。
大丈夫です。一緒に良くしていきましょう。
まずは、1人で悩んでいないで相談してください。









